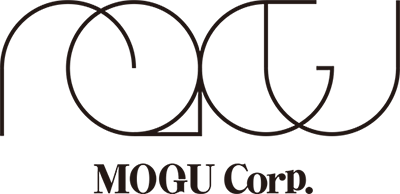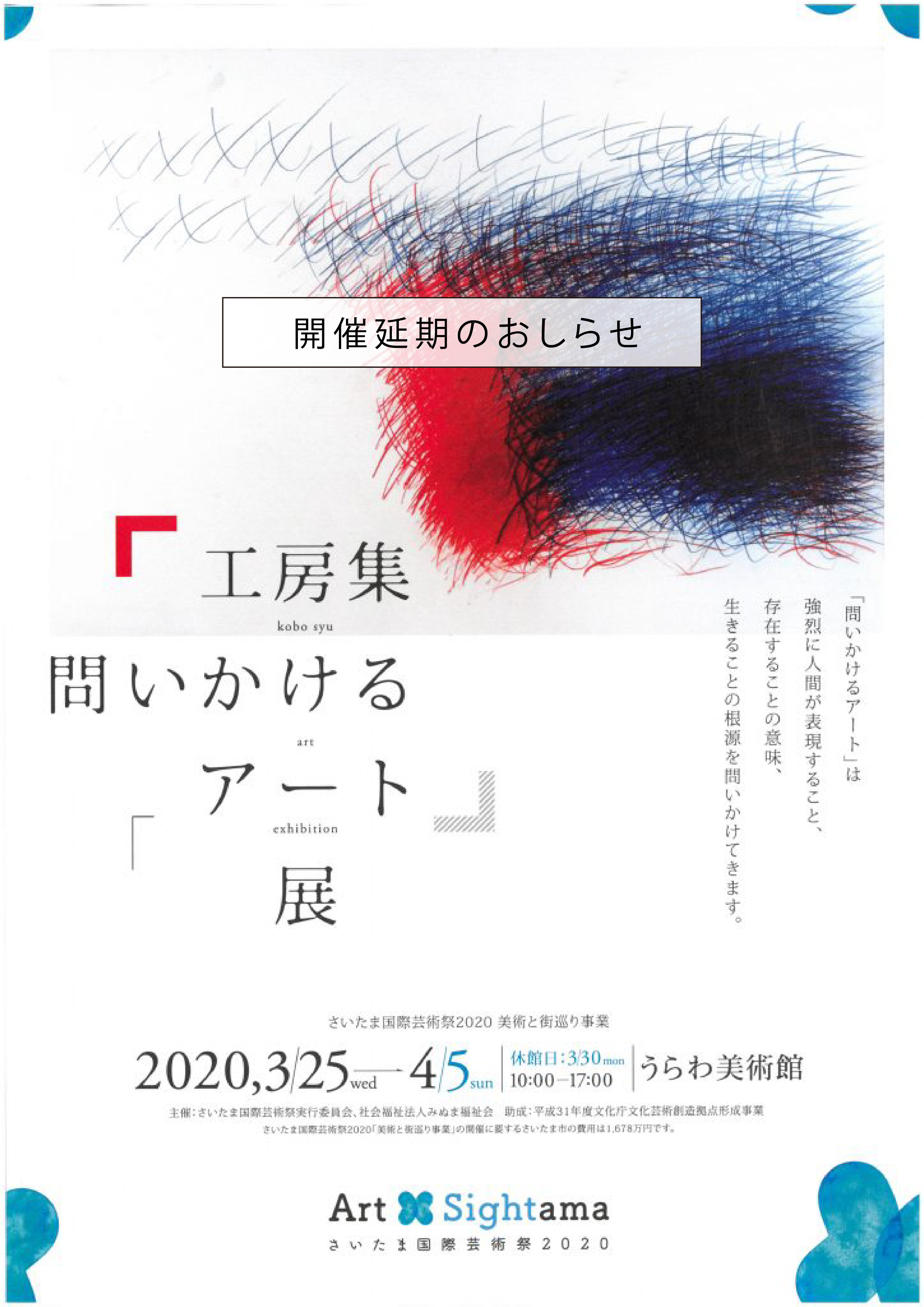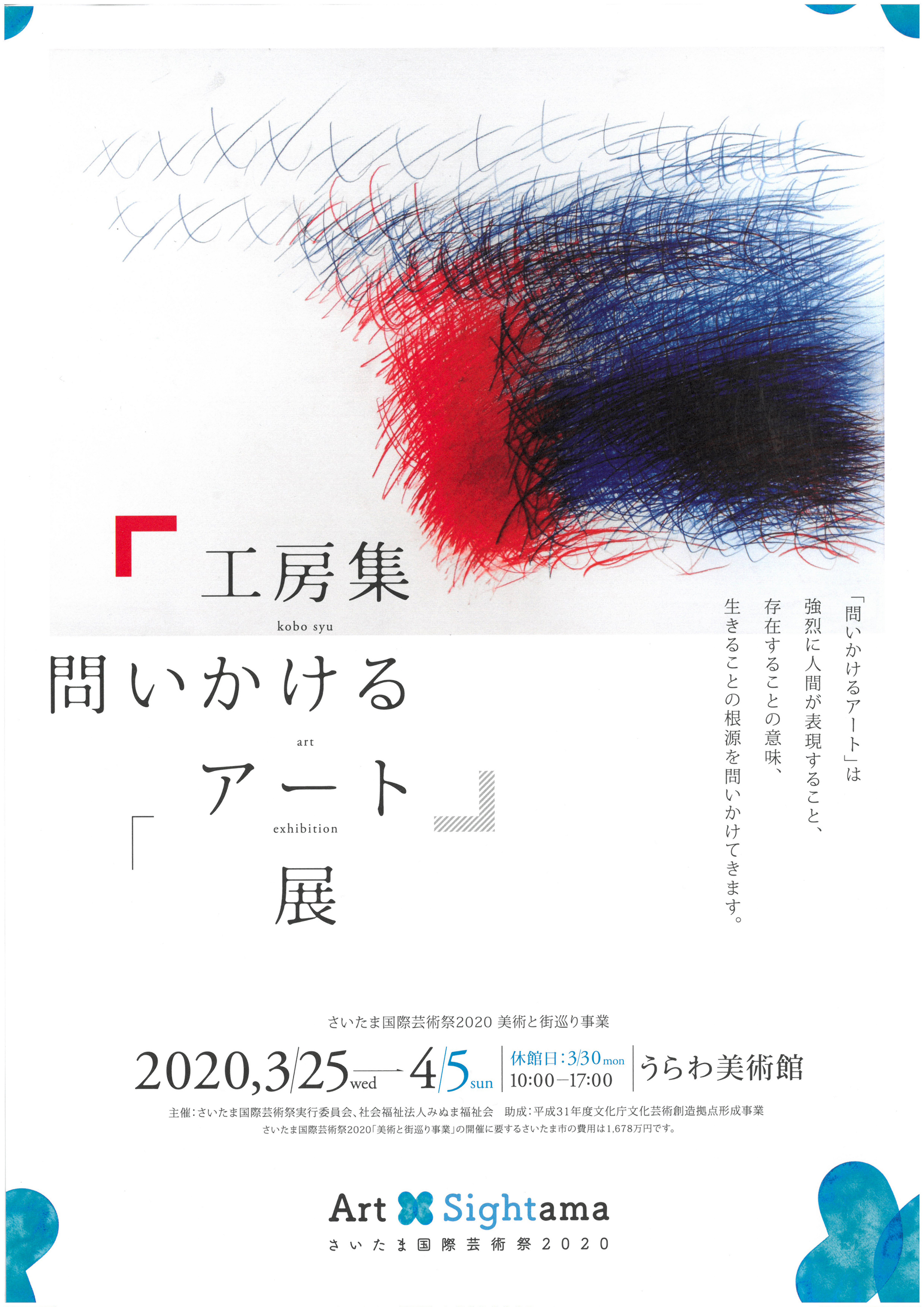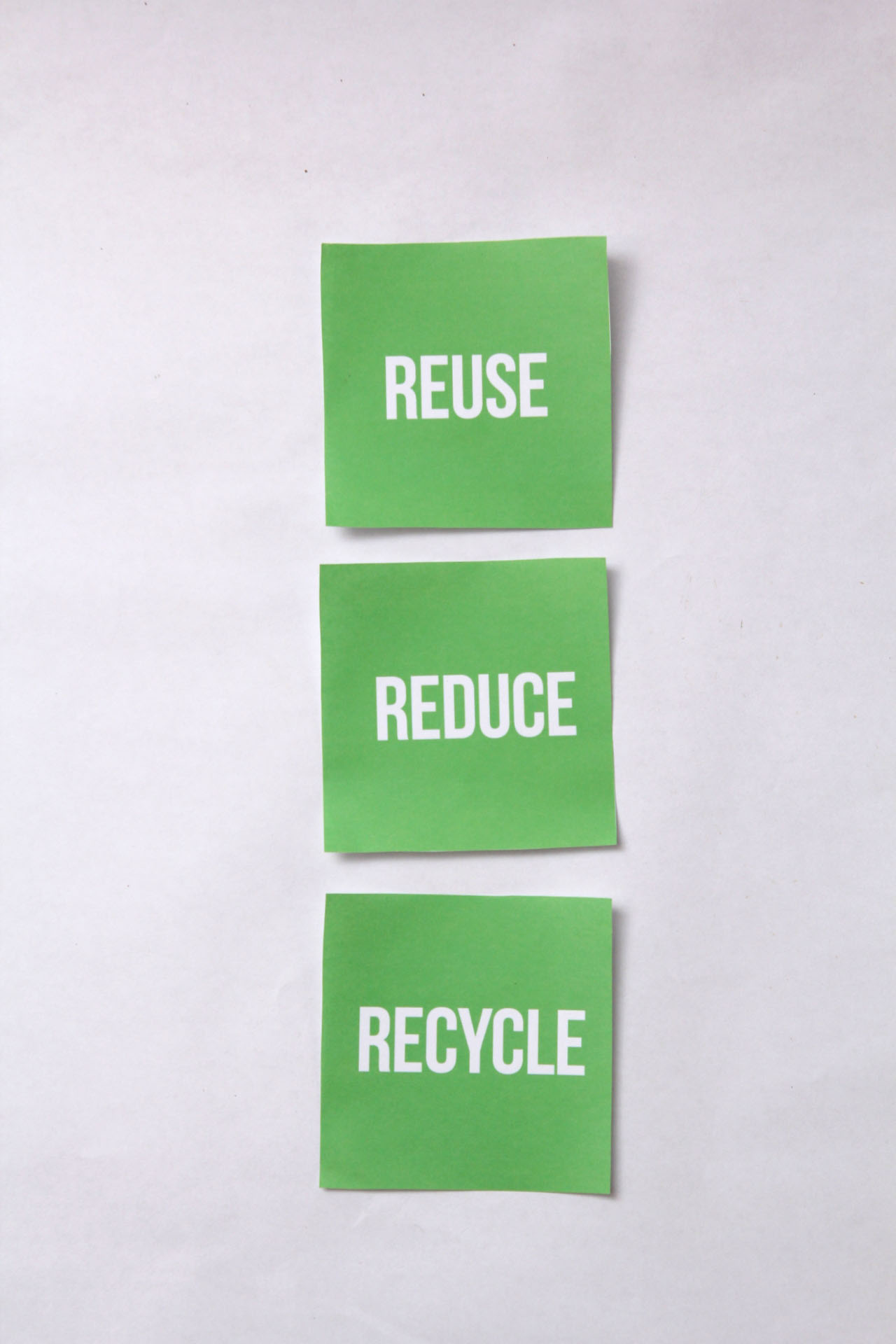NEWS
NEWS 生活にとけこむアートアイテム
ノベルティアイテムのデザインを担当させていただいたので、ご紹介させていただきます。
鉄建建設株式会社様は、毎年「全国安全週間」のタイミングで、従業員や現場を支える関係者のみなさまにオリジナルノベルティグッズを進呈しています。
今年は、両端を引っ張ると一気にたためるエコバッグ「シュパット」に、障がいがあるアーティストの作品を採用して作成したいとのご依頼を一般社団法人障がい者アート協会様にいただき、私どももお手伝いをさせていただきました。
採用されたアートは、立川幹太さんの「働くクルマ」です。
ノベルティグッズは全国1万人以上の方に、レジ袋有料化と同タイミングで配布されました。